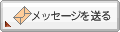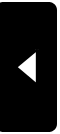2012年04月24日
明後日に
ちょこっと大学生に話をしに行く。
僕もかつて教師を志した。だから、もちろん今の自分がいる。でもね・・・なぜ志したのか。記憶にない。
いやいや、初心を忘れたとかそういうことではなく、なぜ教師になろうと思ったのか。いろんなエクスキューズは身の周りにちらばっているのだけど、それらはまさに後付けのように思えてしまい、それらを司ったその核心が思い出せない。そもそもあったのかどうか・・・。
んじゃ、今は志がなくなったのか?そんなことはない。というより膨大にある。否応なしに歳は重ねられ、志というよりも使命感というような感じだけど。
でも、果たしてこの使命感のようなものを大学生に語るべきなのか。これからこの職業に向けて走り出す若者に、語るべきことなのか。それはあまりにも重い。おそらく鳥の目になってまさに客観的に僕の毎日を眺めることができたら、たくさんの足枷をはめて踊り続ける不憫な中年の姿、それではないかとさえ思う。そこに僕オリジナルな自由はあるのか。自由な意志は発揮されているのか。。。ぼんやりしてしまう。そんな仕事に誰がつきたいと思うのか。
いやいや教職は、僕にとっては最高の仕事であり、これまでの人生の代償であり、「御恩送り」そのものだと思っている。だからこそ、天空を見上げ青々とする大学生にもまた就いてもらいたい仕事であることに違いはない。
でもその切り口が見つからないのよ。この縛られつつ希望を見るような、そんな複雑な感情は、今の僕には軽く語れるものではないのよね。これがおとなということなのでしょうか。それじゃあステレオタイプ。いちいち悩む僕はやはり子どもかな。さてどうしましょう。
僕もかつて教師を志した。だから、もちろん今の自分がいる。でもね・・・なぜ志したのか。記憶にない。
いやいや、初心を忘れたとかそういうことではなく、なぜ教師になろうと思ったのか。いろんなエクスキューズは身の周りにちらばっているのだけど、それらはまさに後付けのように思えてしまい、それらを司ったその核心が思い出せない。そもそもあったのかどうか・・・。
んじゃ、今は志がなくなったのか?そんなことはない。というより膨大にある。否応なしに歳は重ねられ、志というよりも使命感というような感じだけど。
でも、果たしてこの使命感のようなものを大学生に語るべきなのか。これからこの職業に向けて走り出す若者に、語るべきことなのか。それはあまりにも重い。おそらく鳥の目になってまさに客観的に僕の毎日を眺めることができたら、たくさんの足枷をはめて踊り続ける不憫な中年の姿、それではないかとさえ思う。そこに僕オリジナルな自由はあるのか。自由な意志は発揮されているのか。。。ぼんやりしてしまう。そんな仕事に誰がつきたいと思うのか。
いやいや教職は、僕にとっては最高の仕事であり、これまでの人生の代償であり、「御恩送り」そのものだと思っている。だからこそ、天空を見上げ青々とする大学生にもまた就いてもらいたい仕事であることに違いはない。
でもその切り口が見つからないのよ。この縛られつつ希望を見るような、そんな複雑な感情は、今の僕には軽く語れるものではないのよね。これがおとなということなのでしょうか。それじゃあステレオタイプ。いちいち悩む僕はやはり子どもかな。さてどうしましょう。
2012年04月22日
患者立療養所にて
PTA作業を終え、大急ぎで屋我地へ。
とは言っても、勤務校から最短75分かかる。目指すは屋我地島の先の先。今年に入ってから4度目の通園になる。
愛楽園ボランティアガイドの勉強会。年齢も生い立ちも職業も多様なメンバーの多彩な視点にいつも学ばされる。思いが強い分、自分の感情が思考を席巻し、視野が狭くなってしまう。だから自由な発想が交差するここでの勉強会を大事にしたいと思っている。遠かったけれど、今日も行ってよかった。
2時間の勉強会を終え、今日のテーマであった青木恵哉先生のことを考えながら園内をゆっくり見て歩く。途中で海岸に出て砂浜を歩く。大海原を見ながら、このきれいな場所に閉じ込められた人々の思いや、青木先生が抱いた思いって何だったんだろうと考える。
とは言っても、勤務校から最短75分かかる。目指すは屋我地島の先の先。今年に入ってから4度目の通園になる。
愛楽園ボランティアガイドの勉強会。年齢も生い立ちも職業も多様なメンバーの多彩な視点にいつも学ばされる。思いが強い分、自分の感情が思考を席巻し、視野が狭くなってしまう。だから自由な発想が交差するここでの勉強会を大事にしたいと思っている。遠かったけれど、今日も行ってよかった。
2時間の勉強会を終え、今日のテーマであった青木恵哉先生のことを考えながら園内をゆっくり見て歩く。途中で海岸に出て砂浜を歩く。大海原を見ながら、このきれいな場所に閉じ込められた人々の思いや、青木先生が抱いた思いって何だったんだろうと考える。
2012年04月21日
これから
教え方の学習会。第3土曜日。
この学習会に参加してかれこれ4年ほど経つけれど、やっぱり行く前は緊張するよね。なぜって、模擬授業中心の学習会だから。
みんな悪意のまったくない、純粋に力のある教師になりたい前向きなメンバー。すばらしい仲間。だからこそかな、そのみんなの前で授業をして見せるのは気が重い。とても重い。キャリアを積めば積むほど足枷が増えていく。それも自分で付けたものばかり。見せてナンボの商売なのにね。。。まったく情けない。
でもね、僕が無理やりに背筋を伸ばしていられるのは、この不甲斐なさゆえ。不甲斐なさへの抗いこそ、僕の生きるアクセラレータ。まったく難儀な人生よ。
さあて、行ってきます。
この学習会に参加してかれこれ4年ほど経つけれど、やっぱり行く前は緊張するよね。なぜって、模擬授業中心の学習会だから。
みんな悪意のまったくない、純粋に力のある教師になりたい前向きなメンバー。すばらしい仲間。だからこそかな、そのみんなの前で授業をして見せるのは気が重い。とても重い。キャリアを積めば積むほど足枷が増えていく。それも自分で付けたものばかり。見せてナンボの商売なのにね。。。まったく情けない。
でもね、僕が無理やりに背筋を伸ばしていられるのは、この不甲斐なさゆえ。不甲斐なさへの抗いこそ、僕の生きるアクセラレータ。まったく難儀な人生よ。
さあて、行ってきます。
2012年04月20日
2011年12月24日
2011年08月14日
一行詩の授業案
二学期初日に行う予定の授業案である。一学期に何度も取り組ませ慣れ親しんできた
「詩」の新たな学習と、二学期の学級開きを兼ねた内容となっている。なお、この授
業はTOSS青梅教育サークルの村野聡先生の「〈一字題一行詩〉の授業(向山洋一
実践の構想追試)」の修正追試である。
TOSSランド→No.1115215
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
1)「やさしい風が桜を運ぶ」の詩を画面に表示する。
2)先生と一緒に、読みます。さん、はい。もう一回(全員で音読する)
3)これは詩です。一行しかないので「一行詩」と言います。もう一度読んでみよ
う。さん、はい。
4)この一行詩には、漢字一字の題名がついています。「春、夏、秋、冬」のうち
どれだと思いますか?(挙手を求め、どんどん言わせていく)
5)正解は「春」。何で春だと分かった?
数名に理由を聞く(「やさしい風」「桜」とあるから)。理由を聞くことで、一
行詩の作り方(象徴的な言葉を入れて作る)を実感させる。
6)題名から一緒に、読みます。さん、はい。
全員で題名から音読。その後、二つ目の詩「自然が作った大きなわたあめ」を表
示する。
7)題名は何ですか。ノートに書きなさい。ただし、さっきの春夏秋冬とは関係あり
ません。
15秒ほど書くのを待つ。思いつくだけ書かせる。
8)書けた人は起立。一つ言ったら、座ります。言いたい人からどうぞ。
9)正解は「雲」です。題名から一緒に。さん、はい。
全員で題名から音読。その後、三つ目の詩「決してもどらない」を表示する。
10)レベルアップ!題名を書きなさい。
11)お隣さんと見せ合いっこ。
数名を指名して発表させる。同じ答えの人を挙手で確認する。
12)正解は「時」です。題名から。さん、はい。
全員で題名から音読。その後、四つ目の詩「二つあったらいいな」を表示。
13)さらにレベルアップ!題名が書けたら先生に持ってきます。
褒めながら丸をあげ、黒板に書かせる。
14)正解は「命」でした。読みます。さん、はい。
15)これらはすべて、みなさんと同じ六年生が作った一行詩なんです。では、皆さ
んにも作ってもらいます。お題は・・・「夢」です。一つ書けたら先生に持っ
てきます。 │
持ってきた子は褒めて丸をあげ、黒板に書かせる(名前も)。そして、さらに
もう一つ考えさせる。なかなか書けない子は板書を参考にしてもよいと伝える。
16)たくさん書けましたね。すごいね。では、書いたものを発表してもらいます。
黒板に書いたものでも、そうでないものでもいいので一つ読みます。この列か
ら順番にどうぞ。
17)一学期にもたくさん「夢」の話しをしました。「夢」を持つこと、「夢」につ
いて考えること、とても大事なことです。今日から二学期。小学校生活最後の
二学期。大きな「夢」を持って一つひとつ努力できる、そんな二学期にしてい
こうね。 │
「詩」の新たな学習と、二学期の学級開きを兼ねた内容となっている。なお、この授
業はTOSS青梅教育サークルの村野聡先生の「〈一字題一行詩〉の授業(向山洋一
実践の構想追試)」の修正追試である。
TOSSランド→No.1115215
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
1)「やさしい風が桜を運ぶ」の詩を画面に表示する。
2)先生と一緒に、読みます。さん、はい。もう一回(全員で音読する)
3)これは詩です。一行しかないので「一行詩」と言います。もう一度読んでみよ
う。さん、はい。
4)この一行詩には、漢字一字の題名がついています。「春、夏、秋、冬」のうち
どれだと思いますか?(挙手を求め、どんどん言わせていく)
5)正解は「春」。何で春だと分かった?
数名に理由を聞く(「やさしい風」「桜」とあるから)。理由を聞くことで、一
行詩の作り方(象徴的な言葉を入れて作る)を実感させる。
6)題名から一緒に、読みます。さん、はい。
全員で題名から音読。その後、二つ目の詩「自然が作った大きなわたあめ」を表
示する。
7)題名は何ですか。ノートに書きなさい。ただし、さっきの春夏秋冬とは関係あり
ません。
15秒ほど書くのを待つ。思いつくだけ書かせる。
8)書けた人は起立。一つ言ったら、座ります。言いたい人からどうぞ。
9)正解は「雲」です。題名から一緒に。さん、はい。
全員で題名から音読。その後、三つ目の詩「決してもどらない」を表示する。
10)レベルアップ!題名を書きなさい。
11)お隣さんと見せ合いっこ。
数名を指名して発表させる。同じ答えの人を挙手で確認する。
12)正解は「時」です。題名から。さん、はい。
全員で題名から音読。その後、四つ目の詩「二つあったらいいな」を表示。
13)さらにレベルアップ!題名が書けたら先生に持ってきます。
褒めながら丸をあげ、黒板に書かせる。
14)正解は「命」でした。読みます。さん、はい。
15)これらはすべて、みなさんと同じ六年生が作った一行詩なんです。では、皆さ
んにも作ってもらいます。お題は・・・「夢」です。一つ書けたら先生に持っ
てきます。 │
持ってきた子は褒めて丸をあげ、黒板に書かせる(名前も)。そして、さらに
もう一つ考えさせる。なかなか書けない子は板書を参考にしてもよいと伝える。
16)たくさん書けましたね。すごいね。では、書いたものを発表してもらいます。
黒板に書いたものでも、そうでないものでもいいので一つ読みます。この列か
ら順番にどうぞ。
17)一学期にもたくさん「夢」の話しをしました。「夢」を持つこと、「夢」につ
いて考えること、とても大事なことです。今日から二学期。小学校生活最後の
二学期。大きな「夢」を持って一つひとつ努力できる、そんな二学期にしてい
こうね。 │
2011年08月12日
「休暇」という一日に読む
今日は休暇。有り難い。
夏期休暇をきちんと保障されているこの身分というのは、やっぱ、以前の会社の身分
から考えると過保護で、その分がんばらなきゃっと思う。でも休むときは休む。自分
一人の身体ではないからね。自分の子を入れて合計41名の親だと思うと(まあもち
ろん、39名については「お昼の親」ですね)、僕の心の健康は一人事ではないよな。
身体を休め、心を落ち着かせて、安らいで、前向きな気持ちにしていこう。
購入した図書がなんと書斎にある10の本棚からオーバーフローしてきたので、また
また仮の本棚を2つ購入してきて納める。その途上でやっぱり読書。以前に買ってお
いた本を取り出す。

この前、石垣りんさんの詩を授業化したからか、なんとなしにりんさんの詩が載って
いるとこをめくってみる。204ページ。「くらし」。
二連にえぐられる。
にんじんのしっぽ
鳥の骨
父のはらわた
四十の日暮れ
私の目にはじめてあふれる獣の涙
僕が食ってきたもの、僕が便乗したもの、僕が踏み台にしてきたもの、僕が・・・要
領よく利用してきたものを思わないわけにはいかず、ベランダで海を見ながらしばら
く考えても、その全てを到底数えあげることさえできない。
「なんて詩だよ」と思いながら、詩の力を感じる休暇の午後。
夏期休暇をきちんと保障されているこの身分というのは、やっぱ、以前の会社の身分
から考えると過保護で、その分がんばらなきゃっと思う。でも休むときは休む。自分
一人の身体ではないからね。自分の子を入れて合計41名の親だと思うと(まあもち
ろん、39名については「お昼の親」ですね)、僕の心の健康は一人事ではないよな。
身体を休め、心を落ち着かせて、安らいで、前向きな気持ちにしていこう。
購入した図書がなんと書斎にある10の本棚からオーバーフローしてきたので、また
また仮の本棚を2つ購入してきて納める。その途上でやっぱり読書。以前に買ってお
いた本を取り出す。
この前、石垣りんさんの詩を授業化したからか、なんとなしにりんさんの詩が載って
いるとこをめくってみる。204ページ。「くらし」。
二連にえぐられる。
にんじんのしっぽ
鳥の骨
父のはらわた
四十の日暮れ
私の目にはじめてあふれる獣の涙
僕が食ってきたもの、僕が便乗したもの、僕が踏み台にしてきたもの、僕が・・・要
領よく利用してきたものを思わないわけにはいかず、ベランダで海を見ながらしばら
く考えても、その全てを到底数えあげることさえできない。
「なんて詩だよ」と思いながら、詩の力を感じる休暇の午後。
2011年08月11日
島尻教え方学習会!
島尻で教え方の学習会を定期的に主催してる。といっても、参加はたった
2~3名だけれど、中身はなかなかの充実。で、本日はこんな感じ。
*******************************
1)討論で有名な河田孝文先生の学校での授業の様子(VTR)を視聴。
このVTRはコメスが山口県で実際に授業参観させてもらい、録画
したもの。今日は国語の授業を20分間視聴し、お互いに感想を言
い合った。実践場面分析は「視る目」が求められる。視点を確認し
ながら視聴。継続して行い「あれども見えず」の状態を克服したい。
2)模擬授業(T先生)
①5年生「小数」の授業の導入部分。
テンポが悪い、逐一指導になっているなどを指摘し合う。そ
の後、同じ教材を使って参加者全員で代案にチャレンジ。
②「地図帳と地球儀のよさを知ろう」の授業(コメス)
新学習指導要領・社会科の目玉の一つである「地球儀」を使
った授業。地図帳と比較させることで、お互いの特徴やよさ
に気付かせていく。どうやって特徴をつかませ、よさに気付
かせていくかが確定できていない。理解が難しいところなど
を指摘された。
3)参考資料の配付
コメスが南風原町の研修会で使用した「道徳の時間」の授業
作り資料を配付。
*******************************
一つの教材の授業法をみんなで考え、お互いに模擬授業し合う。これが
学習会の醍醐味であり、最も学びの多いところだと思う。一人ひとりで
は乏しいアイディアも、みんなで少しずつ出し合えば次第に良いものに
変化していく。人を相手にして人が作る授業というのは、うまく言えな
いが、そんな実感がある。
次回は8月25日(木)18時より20時
2~3名だけれど、中身はなかなかの充実。で、本日はこんな感じ。
*******************************
1)討論で有名な河田孝文先生の学校での授業の様子(VTR)を視聴。
このVTRはコメスが山口県で実際に授業参観させてもらい、録画
したもの。今日は国語の授業を20分間視聴し、お互いに感想を言
い合った。実践場面分析は「視る目」が求められる。視点を確認し
ながら視聴。継続して行い「あれども見えず」の状態を克服したい。
2)模擬授業(T先生)
①5年生「小数」の授業の導入部分。
テンポが悪い、逐一指導になっているなどを指摘し合う。そ
の後、同じ教材を使って参加者全員で代案にチャレンジ。
②「地図帳と地球儀のよさを知ろう」の授業(コメス)
新学習指導要領・社会科の目玉の一つである「地球儀」を使
った授業。地図帳と比較させることで、お互いの特徴やよさ
に気付かせていく。どうやって特徴をつかませ、よさに気付
かせていくかが確定できていない。理解が難しいところなど
を指摘された。
3)参考資料の配付
コメスが南風原町の研修会で使用した「道徳の時間」の授業
作り資料を配付。
*******************************
一つの教材の授業法をみんなで考え、お互いに模擬授業し合う。これが
学習会の醍醐味であり、最も学びの多いところだと思う。一人ひとりで
は乏しいアイディアも、みんなで少しずつ出し合えば次第に良いものに
変化していく。人を相手にして人が作る授業というのは、うまく言えな
いが、そんな実感がある。
次回は8月25日(木)18時より20時
2011年06月10日
心の支え
ハードな日々を送ってる。
外部からの訪問が重なり、生徒指導担当として奔走させられた。何より僕を疲れさせたのが、学校全体を見渡して答弁するようなやりとり。校長室に呼ばれ、対応の協議を重ねるんだよ。
僕はあくまでプレイヤーだ。学校で言えば、他でもない「担任」という仕事が僕の本業だ。それを棚上げておいて、いわば大局の話しを重ねる。これが僕にはまったく向いていない。「そんなじゃ偉くなんないよ」って言われるけど、プレイヤーとしてこの仕事を選んだのだから、不器用な僕はやはり大局論には戸惑うし、何より学級の子どもたちの未来を考えて試行錯誤を重ねてるときが、立ち位置としてはストンと落ちる。踏ん張りがきくし、何より元気がでる。
そうこうしてるところ、ふらふらっとツタヤに寄ったら、すぐに目についた。キングカズ。

我田引水だけど、「つながってるな」って嬉しくなるよ。何でかって?そこにはこう書かれてたから。
自分が監督に向いてるとは思わない。例えばスタンドから試合を見ても、どの選手の運動量が落ちているだとか、チームのどこをいじれば良くなるかとかいうのがイマイチわからない。/多分、それは僕が基本的に意識を自分に向けてプレーしているから。相手うんぬんよりも、自分が何ができるのか。
『やめないよ』(新潮新書)
当然だけれど、目の前の子どもたちのことを考えるのが僕らの仕事。でも、それを越えて学校がどうのとか、沖縄県の教育施策がどうのとか、今の僕にはまだ重要じゃない。もちろん、目の前の子どもたちのことを考えていけば、そういう大局論にぶつかるのは分かっている。でもそれは今じゃない。今、肝心なのは毎日飽きるほど顔をつきあわせるあの子たちをどう成長させ、どう笑顔にさせるかってこと。そういう意味で、僕はまだプレイヤーでありたい。どんな子でもひっくるめて引っ張り続けるプレイヤーで。
外部からの訪問が重なり、生徒指導担当として奔走させられた。何より僕を疲れさせたのが、学校全体を見渡して答弁するようなやりとり。校長室に呼ばれ、対応の協議を重ねるんだよ。
僕はあくまでプレイヤーだ。学校で言えば、他でもない「担任」という仕事が僕の本業だ。それを棚上げておいて、いわば大局の話しを重ねる。これが僕にはまったく向いていない。「そんなじゃ偉くなんないよ」って言われるけど、プレイヤーとしてこの仕事を選んだのだから、不器用な僕はやはり大局論には戸惑うし、何より学級の子どもたちの未来を考えて試行錯誤を重ねてるときが、立ち位置としてはストンと落ちる。踏ん張りがきくし、何より元気がでる。
そうこうしてるところ、ふらふらっとツタヤに寄ったら、すぐに目についた。キングカズ。
我田引水だけど、「つながってるな」って嬉しくなるよ。何でかって?そこにはこう書かれてたから。
自分が監督に向いてるとは思わない。例えばスタンドから試合を見ても、どの選手の運動量が落ちているだとか、チームのどこをいじれば良くなるかとかいうのがイマイチわからない。/多分、それは僕が基本的に意識を自分に向けてプレーしているから。相手うんぬんよりも、自分が何ができるのか。
『やめないよ』(新潮新書)
当然だけれど、目の前の子どもたちのことを考えるのが僕らの仕事。でも、それを越えて学校がどうのとか、沖縄県の教育施策がどうのとか、今の僕にはまだ重要じゃない。もちろん、目の前の子どもたちのことを考えていけば、そういう大局論にぶつかるのは分かっている。でもそれは今じゃない。今、肝心なのは毎日飽きるほど顔をつきあわせるあの子たちをどう成長させ、どう笑顔にさせるかってこと。そういう意味で、僕はまだプレイヤーでありたい。どんな子でもひっくるめて引っ張り続けるプレイヤーで。
2011年05月25日
降りていくところ
生きるとは、たぶん判断することだと思う。他でもない自分が。
そのとき、そこで、どう判断し行動したか。。。その集積が人生かと。
なら、教育とはその判断をする材料をどれだけ提供できるかに係る。
僕たちがやっていることは、つまるとこそういうことなのかなと、ふと思う。
国語、算数、理科、社会・・・。いろいろ教えるよ、現場では。
でも僕らはそれを通して、社会通念というか倫理というか、そういうものを
教えているのだろう。もちろん、各論的なハンドリングは教えつつ、でもつ
まるところそうかなと。
そうこう考えてるとやっぱり突き当たる。
何よりもまず自分の生を基本的に肯定していること、それがあらゆる倫理性
の基盤であって、その逆ではない。だから、子供の教育において、第一にな
すべきことは、道徳を教えることではなく、人生が楽しいということを、つ
まり自己の生が根源において肯定されるべきものであることを、体に覚え込
ませてやることなのである
(永井均著『これがニーチェだ』講談社学術文庫)
永井先生がニーチェを通じて語ったこの言葉。僕は壁に突き当たるといつも、そういつもこの言葉をトレースする。
学校楽しいか?学級はどうだ?根拠などなくても、将来への、いやこれから
の自分への淡い期待は抱けてるかな。
僕はそう仕向ける先生になれてるかな。
そのとき、そこで、どう判断し行動したか。。。その集積が人生かと。
なら、教育とはその判断をする材料をどれだけ提供できるかに係る。
僕たちがやっていることは、つまるとこそういうことなのかなと、ふと思う。
国語、算数、理科、社会・・・。いろいろ教えるよ、現場では。
でも僕らはそれを通して、社会通念というか倫理というか、そういうものを
教えているのだろう。もちろん、各論的なハンドリングは教えつつ、でもつ
まるところそうかなと。
そうこう考えてるとやっぱり突き当たる。
何よりもまず自分の生を基本的に肯定していること、それがあらゆる倫理性
の基盤であって、その逆ではない。だから、子供の教育において、第一にな
すべきことは、道徳を教えることではなく、人生が楽しいということを、つ
まり自己の生が根源において肯定されるべきものであることを、体に覚え込
ませてやることなのである
(永井均著『これがニーチェだ』講談社学術文庫)
永井先生がニーチェを通じて語ったこの言葉。僕は壁に突き当たるといつも、そういつもこの言葉をトレースする。
学校楽しいか?学級はどうだ?根拠などなくても、将来への、いやこれから
の自分への淡い期待は抱けてるかな。
僕はそう仕向ける先生になれてるかな。