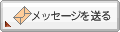2008年02月17日
「疲れた」だと!!
僕は親でもある。
二男児の父なのだ。われながら甚だ心許ない。
でも父なのである。
久しぶりの晴天(うれしー)だったので、息子の要求を呑み、午
後から自転車を乗りにドコモ公園へ行く。
雨降り続きで自転車の練習がままならなかったのだけれど、な
かなか上手である。感を掴んだ感じ。
そこで事件が起こった(すみません、おおげさです)。
たった15分が経過したとき、たった15分である。わが軟派な
長男が言い放った。
「お父さん、もう疲れたからお家でポケモン観る」と。
は?
「自転車苦手だから、家でポケモン観たい」。
どっかーん(怒)!!!である。
怒った理由が二つある。
①わざわざ人が多い公園まで来させておいて、
すぐに帰ると言ったこと。
②「疲れた」「苦手」という言葉を使ったこと。
①に関してはいい。今後、子どもの要求に簡単に腰を上げなけ
ればいいのである。しばらくすれば、自分から要求したことへの
耐性はついてくる。
問題は②だと思う。「疲れた」「苦手」というのは、いってみれば、
プラセボ効果的言葉である。あれである。偽物の薬なのに、何
故か効果があるというあれ。偽薬効果。その詰まるところは、
思い込みによる心理的バイアスの強さを明らかにしている。
僕が子育てで、学校での子どもとのやりとりで気をつけているこ
とのベスト10の中に、このプラセボ語を使わない、使わせないと
いうものがある。これはかなり意識的に行っている。
簡単に言うととても簡単なことである。子どもに「疲れたの~」と
聞くと、子どもの中に「疲れた(からやらない)」という心理的スペ
ースが生まれる。子どもに「苦手なの~」というと、「苦手(なので
やらない)」という心理的スペースが生まれる。子どもに「ストレス
溜まってるの?」と聞くと、「ストレス(が溜まってるのでダルイ)」
という心理的スペースが生まれる。
そういうことである。
こういうことを、教育相談・カウンセリング専門の方々に披露すると、
必ず嫌な顔をされる。「あなたがやっていることは、子どもを追いつ
めることよ」という顔である。
でも、僕は追いつめられた子どもの顔は、言わなくとも分かるの
ではないか・・・と思っている。特に親なら、小学校担任なら。ね。
その子の明るい顔、真剣な顔、困った顔、悲しい顔というのを日
々見ている僕たちなら、「やばい」時は分からなくてはいけないと
強く思う。プロを意識したいから、そういう気持ちで子どもと向き合
いたいと思い、毎日せっせと他愛もない会話を子どもたち全員と
するのである(一日に最低2回は全員と、一言でもいいので個別
にしゃべる)。
何だか話が逸れたので戻ります。
僕は今日、わが子がプラセボ語をいとも簡単に駆使したことに、
怒りとともに驚いた。誰がたった4歳児にそんな言葉、教えたの
だ~!!!(予測可能だが)。
子どもならずとも、人間には壁が必要だと思う。いわんやまだ
柔らかい形成段階にある子どもなら、それはなおさらであると
思う。壁にぶち当たる。それをかなり無理して乗り越えたとき、
一定の力がつく。だから、どんどん無理をさせる。僕ならこうい
う言葉をつかう。「ね、簡単でしょ」「もっとできるはずよ」「今日
は(教える)オレが疲れたから終わる」などなど。言葉はいつも
前へ口をパカっと開くように心がける。
程度の低い無理から、程度の高い無理へという教育的配慮を
行うのが、いわば我々の職務である。もちろん親としての職務
でもあると思う(と僕は思う)。そこに安易にプラセボ語を持って
きてしまうと、も終わりである。一瞬にして壁は消失する。どん
なに大きく硬い壁と言えども、プラセボ語の前では非力なので
ある。恐るべしプラセボ語。
再び公園にて
「〈疲れた〉ってどういう意味かー!!」「〈苦手〉って何かー!」
と鼻を最大限に膨らませながらたった4歳の子を問い詰める。
どつく(ひどい親だ)。彼は泣きながら言った・・・
「分からん」
「分からんかったら使うな」(父)
(沈黙)
自分の返答の貧しさに打ちひしがれ、それでもお互い「帰ろう」と
すぐに切り出すことができず、黙って鉄棒をしたり、平均台をした
りしてた。息子は、思ってた通り、全然疲れてなどいなかった。
だろ~。だろ~。そうだろ~。
それにしても、そもそも子どもが「疲れた~」と言わない時間の使
い方をしなきゃな。これ学校でもしかり。不甲斐ないな全く。
二男児の父なのだ。われながら甚だ心許ない。
でも父なのである。
久しぶりの晴天(うれしー)だったので、息子の要求を呑み、午
後から自転車を乗りにドコモ公園へ行く。
雨降り続きで自転車の練習がままならなかったのだけれど、な
かなか上手である。感を掴んだ感じ。
そこで事件が起こった(すみません、おおげさです)。
たった15分が経過したとき、たった15分である。わが軟派な
長男が言い放った。
「お父さん、もう疲れたからお家でポケモン観る」と。
は?
「自転車苦手だから、家でポケモン観たい」。
どっかーん(怒)!!!である。
怒った理由が二つある。
①わざわざ人が多い公園まで来させておいて、
すぐに帰ると言ったこと。
②「疲れた」「苦手」という言葉を使ったこと。
①に関してはいい。今後、子どもの要求に簡単に腰を上げなけ
ればいいのである。しばらくすれば、自分から要求したことへの
耐性はついてくる。
問題は②だと思う。「疲れた」「苦手」というのは、いってみれば、
プラセボ効果的言葉である。あれである。偽物の薬なのに、何
故か効果があるというあれ。偽薬効果。その詰まるところは、
思い込みによる心理的バイアスの強さを明らかにしている。
僕が子育てで、学校での子どもとのやりとりで気をつけているこ
とのベスト10の中に、このプラセボ語を使わない、使わせないと
いうものがある。これはかなり意識的に行っている。
簡単に言うととても簡単なことである。子どもに「疲れたの~」と
聞くと、子どもの中に「疲れた(からやらない)」という心理的スペ
ースが生まれる。子どもに「苦手なの~」というと、「苦手(なので
やらない)」という心理的スペースが生まれる。子どもに「ストレス
溜まってるの?」と聞くと、「ストレス(が溜まってるのでダルイ)」
という心理的スペースが生まれる。
そういうことである。
こういうことを、教育相談・カウンセリング専門の方々に披露すると、
必ず嫌な顔をされる。「あなたがやっていることは、子どもを追いつ
めることよ」という顔である。
でも、僕は追いつめられた子どもの顔は、言わなくとも分かるの
ではないか・・・と思っている。特に親なら、小学校担任なら。ね。
その子の明るい顔、真剣な顔、困った顔、悲しい顔というのを日
々見ている僕たちなら、「やばい」時は分からなくてはいけないと
強く思う。プロを意識したいから、そういう気持ちで子どもと向き合
いたいと思い、毎日せっせと他愛もない会話を子どもたち全員と
するのである(一日に最低2回は全員と、一言でもいいので個別
にしゃべる)。
何だか話が逸れたので戻ります。
僕は今日、わが子がプラセボ語をいとも簡単に駆使したことに、
怒りとともに驚いた。誰がたった4歳児にそんな言葉、教えたの
だ~!!!(予測可能だが)。
子どもならずとも、人間には壁が必要だと思う。いわんやまだ
柔らかい形成段階にある子どもなら、それはなおさらであると
思う。壁にぶち当たる。それをかなり無理して乗り越えたとき、
一定の力がつく。だから、どんどん無理をさせる。僕ならこうい
う言葉をつかう。「ね、簡単でしょ」「もっとできるはずよ」「今日
は(教える)オレが疲れたから終わる」などなど。言葉はいつも
前へ口をパカっと開くように心がける。
程度の低い無理から、程度の高い無理へという教育的配慮を
行うのが、いわば我々の職務である。もちろん親としての職務
でもあると思う(と僕は思う)。そこに安易にプラセボ語を持って
きてしまうと、も終わりである。一瞬にして壁は消失する。どん
なに大きく硬い壁と言えども、プラセボ語の前では非力なので
ある。恐るべしプラセボ語。
再び公園にて
「〈疲れた〉ってどういう意味かー!!」「〈苦手〉って何かー!」
と鼻を最大限に膨らませながらたった4歳の子を問い詰める。
どつく(ひどい親だ)。彼は泣きながら言った・・・
「分からん」
「分からんかったら使うな」(父)
(沈黙)
自分の返答の貧しさに打ちひしがれ、それでもお互い「帰ろう」と
すぐに切り出すことができず、黙って鉄棒をしたり、平均台をした
りしてた。息子は、思ってた通り、全然疲れてなどいなかった。
だろ~。だろ~。そうだろ~。
それにしても、そもそも子どもが「疲れた~」と言わない時間の使
い方をしなきゃな。これ学校でもしかり。不甲斐ないな全く。
Posted by sky1973629 at 16:45│Comments(0)
│教えること育てること