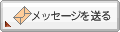2008年02月04日
まやかし論再考
過日、「夢」を持たせようとする教育の在り方を「まやかし」と書いた。
その内容を知人に話すと、「そりゃあそうでも、致し方なし」と論破される。
まあそうだな。
「夢→目的意識(意欲)→向社会的行動」というベクトルは、教育的には正論だ。致し方ないのも
致し方なしか。時宜を得て、津覇実明さんの小論(「暮らしを守る競争 必要」沖縄タイムス2008
/2/4)にダメ押される。
「(夢や目標は)将来どうやって稼ぎ、食っていくかというレベルの職業観が伴わなければ、ただ
の夢想にすぎない」「目的意識と意欲、向上心は密接に結び付いている。中学、高校でもっと本
腰を入れて職場体験に取り組むべきだ」
彼の言葉は強いな。塾講という現場で叩き上げられたものだ。太刀打ちしがたい。
教育に携わる者の使命の第一義は、子どもに学ぶ必要性を実感させ、勉学やその他諸々の活
動に勤しませ、そういうことの中で社会で生き抜く術を与えること。つまり、「自立を促す」(津覇)
ことに他ならない。のは、分かってるのよ。もちろん。
でもさ、でもね・・・(やっぱ学校の教員は甘っちょろいと言われるの覚悟でね)・・・教育関係者総
自己実現論者という画一的なものの中にどっぷりと浸ると(もちろん僕もその実践者であります)
ね、背筋がゾクゾクゾクってなるのですよ。
「夢」ってのはあれでしょ。
人生を楽しく有意義なものにしてくれるものでしょ。
「夢」を持ったとき、こんな面倒な世の中なのにさ、未来が楽しいじゃない。
インディージョーンズになって埋蔵金ゲットできるかも・・・って考えると胸が弾むじゃない。
デロリアンに乗って過去や未来に行ける!って夢想すると、ドキドキするじゃない。
それが「夢」ってもんじゃないの?(これ僕の率直な実感でございます)
そんなステキな「夢」がさ、なんか勉学(向社会的行動)を強いるための都合良い道具になって
いる現状は貧しすぎるのですよ。
僕はこういうのを望む(これもまた「夢」)。
「目の前のことに楽しく取り組んでたら、こんなチャンスが巡ってきました!」
「なんてすごいチャンス!これって〈夢〉かも?」
「そうかー、僕はこんな〈夢〉のためにこれまで努力してきたんだなぁ。あー、僕って自己実現した
のね・・・」
※ここには「夢」のすり替えと、過去をふり返る際の脚色が付与されています(cf.浅野智彦著『自己への物語論的接近』勁草書房)
そんなことを下書きし、その続きを考えてたら、やっぱ出逢うのです。恐るべし潜在意識。
「小さい頃から〈夢を持て!〉とか、〈大きな夢を実現する大人になれ〉と言われて育つと、ついつ
い〈夢〉を持たなければ生きていけないのか、と勘違いする。/結果、〈私には夢がない〉という恐
怖に打ちひしがれ、〈夢の不在症候群〉にかかってしまう。(中略)しかし、はっきり姿を持った〈夢〉
を持ち、それを追いかけている大人は、世の中にどれほどいるだろうか。むしろ、大半は、日常の
試行錯誤の中に、〈夢〉というほど格好良くはないけれど、霧の中でときどき薄日が射す方向が見
えて来ることもある、というように生きている。/だから、子どもたちも、安心してほしい」
(藤原和博著『新しい道徳』ちくまプリマー新書2007)

藤原さん、ありがとう(拝)。
とはいえ、藤原さんとは、今「よるスペ」で話題沸騰中でかの和田中学校の、そう、校長先生で
す。もちろん立場上キャリア教育を推進・実践する張本人でもあります。そんなエライ人がこん
なこと言ってくれるのですよ(涙)。
んー、やっぱ大切なのは懐の広さだな。
夢を持ちたい奴は持て!持てない奴も心配するな!すべてオレが面倒見てやる。
様々な子どもたちを片っ端から受け入れていく、そんな巨大な器になりたいものです。
はい、机上論は終わり。
まずは「夢(将来)」という担保がなくても、子どもがモリモリと授業に臨み、バリバリと高度な問
題に挑戦し、「おれはできる!」と実感できるような授業を打つことだな。あー教材研究難しいさぁ。
よし!明日のためにTOSSでも開きましょうか。向山先生、よろしくお願いします。
その内容を知人に話すと、「そりゃあそうでも、致し方なし」と論破される。
まあそうだな。
「夢→目的意識(意欲)→向社会的行動」というベクトルは、教育的には正論だ。致し方ないのも
致し方なしか。時宜を得て、津覇実明さんの小論(「暮らしを守る競争 必要」沖縄タイムス2008
/2/4)にダメ押される。
「(夢や目標は)将来どうやって稼ぎ、食っていくかというレベルの職業観が伴わなければ、ただ
の夢想にすぎない」「目的意識と意欲、向上心は密接に結び付いている。中学、高校でもっと本
腰を入れて職場体験に取り組むべきだ」
彼の言葉は強いな。塾講という現場で叩き上げられたものだ。太刀打ちしがたい。
教育に携わる者の使命の第一義は、子どもに学ぶ必要性を実感させ、勉学やその他諸々の活
動に勤しませ、そういうことの中で社会で生き抜く術を与えること。つまり、「自立を促す」(津覇)
ことに他ならない。のは、分かってるのよ。もちろん。
でもさ、でもね・・・(やっぱ学校の教員は甘っちょろいと言われるの覚悟でね)・・・教育関係者総
自己実現論者という画一的なものの中にどっぷりと浸ると(もちろん僕もその実践者であります)
ね、背筋がゾクゾクゾクってなるのですよ。
「夢」ってのはあれでしょ。
人生を楽しく有意義なものにしてくれるものでしょ。
「夢」を持ったとき、こんな面倒な世の中なのにさ、未来が楽しいじゃない。
インディージョーンズになって埋蔵金ゲットできるかも・・・って考えると胸が弾むじゃない。
デロリアンに乗って過去や未来に行ける!って夢想すると、ドキドキするじゃない。
それが「夢」ってもんじゃないの?(これ僕の率直な実感でございます)
そんなステキな「夢」がさ、なんか勉学(向社会的行動)を強いるための都合良い道具になって
いる現状は貧しすぎるのですよ。
僕はこういうのを望む(これもまた「夢」)。
「目の前のことに楽しく取り組んでたら、こんなチャンスが巡ってきました!」
「なんてすごいチャンス!これって〈夢〉かも?」
「そうかー、僕はこんな〈夢〉のためにこれまで努力してきたんだなぁ。あー、僕って自己実現した
のね・・・」
※ここには「夢」のすり替えと、過去をふり返る際の脚色が付与されています(cf.浅野智彦著『自己への物語論的接近』勁草書房)
そんなことを下書きし、その続きを考えてたら、やっぱ出逢うのです。恐るべし潜在意識。
「小さい頃から〈夢を持て!〉とか、〈大きな夢を実現する大人になれ〉と言われて育つと、ついつ
い〈夢〉を持たなければ生きていけないのか、と勘違いする。/結果、〈私には夢がない〉という恐
怖に打ちひしがれ、〈夢の不在症候群〉にかかってしまう。(中略)しかし、はっきり姿を持った〈夢〉
を持ち、それを追いかけている大人は、世の中にどれほどいるだろうか。むしろ、大半は、日常の
試行錯誤の中に、〈夢〉というほど格好良くはないけれど、霧の中でときどき薄日が射す方向が見
えて来ることもある、というように生きている。/だから、子どもたちも、安心してほしい」
(藤原和博著『新しい道徳』ちくまプリマー新書2007)
藤原さん、ありがとう(拝)。
とはいえ、藤原さんとは、今「よるスペ」で話題沸騰中でかの和田中学校の、そう、校長先生で
す。もちろん立場上キャリア教育を推進・実践する張本人でもあります。そんなエライ人がこん
なこと言ってくれるのですよ(涙)。
んー、やっぱ大切なのは懐の広さだな。
夢を持ちたい奴は持て!持てない奴も心配するな!すべてオレが面倒見てやる。
様々な子どもたちを片っ端から受け入れていく、そんな巨大な器になりたいものです。
はい、机上論は終わり。
まずは「夢(将来)」という担保がなくても、子どもがモリモリと授業に臨み、バリバリと高度な問
題に挑戦し、「おれはできる!」と実感できるような授業を打つことだな。あー教材研究難しいさぁ。
よし!明日のためにTOSSでも開きましょうか。向山先生、よろしくお願いします。
Posted by sky1973629 at 18:08│Comments(0)
│教えること育てること