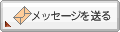2008年09月17日
ぎせいギセイぎせい
凛MM さん、嬉しいメルほんとにありがと。
魂のある言葉・・・そういうのを「ここぞ」という場面で言える、そんな人間になりたい。つくづくそう思います(後になって思うことがまだまだ多くて・・・なかなか「ここぞ」では言えないんだよね。教員としても親としてもさあ)。そして何よりも行動。行動が伴わないとさ、その言葉は百害あって一利なしよね。がんばろ。
さてさてところで、僕の敬服する平川克美さんが、リーマン倒産に際してすっごくいいコメントを記している。
http://plaza.rakuten.co.jp/hirakawadesu/diary/200809160000/
「多かれ少なかれ社会というものは、ひとつの擬制(フィクション)の上でしか運営してゆくことはできないからだ」という平川さんの言葉にはずしんときた。
平川さんはここで、社会思想やら国家理念について、それを「ひとつの擬制」というふうに書いてる。でも「ひとつの擬制」については、何も大局に限らない。僕たちが日々、子どもや同僚の間でとりおこなわれるやりとりの中にも、この「ひとつの擬制」は確実にちゃっかり働いてる。
例えば、僕らの「教育」という仕事は(これは親業もそうなのだろうと思うけれど)、「努力」とか「目標(めあて)」とか「夢」とか「自己実現」とか「協力」とか「助け合い」とか・・・、そういうトリックワードで埋め尽くされてる。「もっと努力しなさい」「夢は必ず叶う」とか「目標のあるところに道は開ける」とか「人は助け合って生きていくものです」とか何とか・・・、そういう言葉を教師は語る。いやいや、「語る」と言えるほどの主体性はそこにはない、と言ってもいい。そうではなくて、それを「語ら」なくては、僕たちの仕事は成り立たない。ゆえに「語ら」ざるを得ない、というのが正確な表現ではないかと思う。それほど、これらのトリッキーな言葉に支えられて、僕らの仕事はどうにか道を踏み外さずに歩むことができるのである。でもでも、それってほんとにすべてそういうことが当てはまるほど、世の中は単純には出来ていない。真面目な人がバカを見る、大きな夢を持ったがゆえに転ぶやつがいる、目標なんてなくても別に問題なし、現に新聞では思いやりのないことで埋め尽くされてばかり。
勝手に熱くなってきたけど・・・もうねんねの時間(笑)。なので、そろそろ終わりにする。
僕は平川さんの次の言葉に、やっぱり感動する。
「だが、同時にお金が行使できるパワーは極めて限定的なものであり、それを万能だと思うことは恥ずかしいことなのだという認識をお金が重要であると考える同じ分だけ帯同すべきなのである。擬制は、自らそれが擬制であることを知り、もっと控えめであるべきなのだ」
平川さんは、会社経営者であり、たぶん投資家でもある。情報社会の産物である株を買い、そこから利益を得る現代的な人間そのものである。程度の差はあれ、お金への信仰によって成り立つ市場に生きる人間である。そんなお前が何を言ってんだ、とは僕は思わない。そういう人間がこんな発言をする、ということに勇気と叡智と誠実さを感じる。
僕は子らに「努力をしなさい」と言う。「思いやりを持ちなさい」と言う。はっきりとしっかりと、時に威圧的に言う。でも、そこからはみ出た人間を、そんな人間こそを掬いたいと思う。その人間臭さが好きでたまらない。受け止めたい。これは許容するということじゃない。同じ轍を踏んだ人間として、それを受け止めてやりたいと思ってる。また0から、いやマイナスから一緒に始めればいいさ、ね。「擬制にもっと控えめであるべきだ」という平川さんの言葉から、僕はそんなことを考えた。
幅のある人間になりたい。のりしろのある人間に。
その割り切れない曖昧な部分、そこに生まれるものが「優しさ」であり、「愛」なんじゃないかな、って大袈裟に思ってる。
魂のある言葉・・・そういうのを「ここぞ」という場面で言える、そんな人間になりたい。つくづくそう思います(後になって思うことがまだまだ多くて・・・なかなか「ここぞ」では言えないんだよね。教員としても親としてもさあ)。そして何よりも行動。行動が伴わないとさ、その言葉は百害あって一利なしよね。がんばろ。
さてさてところで、僕の敬服する平川克美さんが、リーマン倒産に際してすっごくいいコメントを記している。
http://plaza.rakuten.co.jp/hirakawadesu/diary/200809160000/
「多かれ少なかれ社会というものは、ひとつの擬制(フィクション)の上でしか運営してゆくことはできないからだ」という平川さんの言葉にはずしんときた。
平川さんはここで、社会思想やら国家理念について、それを「ひとつの擬制」というふうに書いてる。でも「ひとつの擬制」については、何も大局に限らない。僕たちが日々、子どもや同僚の間でとりおこなわれるやりとりの中にも、この「ひとつの擬制」は確実にちゃっかり働いてる。
例えば、僕らの「教育」という仕事は(これは親業もそうなのだろうと思うけれど)、「努力」とか「目標(めあて)」とか「夢」とか「自己実現」とか「協力」とか「助け合い」とか・・・、そういうトリックワードで埋め尽くされてる。「もっと努力しなさい」「夢は必ず叶う」とか「目標のあるところに道は開ける」とか「人は助け合って生きていくものです」とか何とか・・・、そういう言葉を教師は語る。いやいや、「語る」と言えるほどの主体性はそこにはない、と言ってもいい。そうではなくて、それを「語ら」なくては、僕たちの仕事は成り立たない。ゆえに「語ら」ざるを得ない、というのが正確な表現ではないかと思う。それほど、これらのトリッキーな言葉に支えられて、僕らの仕事はどうにか道を踏み外さずに歩むことができるのである。でもでも、それってほんとにすべてそういうことが当てはまるほど、世の中は単純には出来ていない。真面目な人がバカを見る、大きな夢を持ったがゆえに転ぶやつがいる、目標なんてなくても別に問題なし、現に新聞では思いやりのないことで埋め尽くされてばかり。
勝手に熱くなってきたけど・・・もうねんねの時間(笑)。なので、そろそろ終わりにする。
僕は平川さんの次の言葉に、やっぱり感動する。
「だが、同時にお金が行使できるパワーは極めて限定的なものであり、それを万能だと思うことは恥ずかしいことなのだという認識をお金が重要であると考える同じ分だけ帯同すべきなのである。擬制は、自らそれが擬制であることを知り、もっと控えめであるべきなのだ」
平川さんは、会社経営者であり、たぶん投資家でもある。情報社会の産物である株を買い、そこから利益を得る現代的な人間そのものである。程度の差はあれ、お金への信仰によって成り立つ市場に生きる人間である。そんなお前が何を言ってんだ、とは僕は思わない。そういう人間がこんな発言をする、ということに勇気と叡智と誠実さを感じる。
僕は子らに「努力をしなさい」と言う。「思いやりを持ちなさい」と言う。はっきりとしっかりと、時に威圧的に言う。でも、そこからはみ出た人間を、そんな人間こそを掬いたいと思う。その人間臭さが好きでたまらない。受け止めたい。これは許容するということじゃない。同じ轍を踏んだ人間として、それを受け止めてやりたいと思ってる。また0から、いやマイナスから一緒に始めればいいさ、ね。「擬制にもっと控えめであるべきだ」という平川さんの言葉から、僕はそんなことを考えた。
幅のある人間になりたい。のりしろのある人間に。
その割り切れない曖昧な部分、そこに生まれるものが「優しさ」であり、「愛」なんじゃないかな、って大袈裟に思ってる。
Posted by sky1973629 at 23:49│Comments(0)
│日常