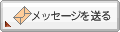2008年05月29日
ふと思う
忙殺されている。
担任という仕事に。そして生徒指導という公務に。
溺れつつある。悲しいかなほとんどが事務作業。「急ぎ」と書かれた
資料に追い回され目眩を感じたので、すべてを一度休止し、机の整
理から始める。主にファイリング。机がきれいになっていく過程で、
頭もすっきりしてくる。仕事の優先順位が見えてくる。
整理整頓。あなどれない。
忙しいと、やはりたくさんの人との接触がある。確認しないといけな
いことばかりだから。その中で、偶然にも怯えた人に何人か出逢う。
誰に。
権力に。上司に。保護者に。そして子どもに。
怯えることは大事であると思う。恐怖心は仕事を細やかなものにす
る。恐れのない者は、勢いで賄えなくなると廃る。そのことは、もう
経験上痛感している、つもり。だってもうすぐ35なのですから(とは
言いつつも、「お前の仕事は力業だな」と叱られることは多々ある。
まだ35の青二才とも言える)。
だけど、あまりに恐怖心を持っている人に出逢うと、何だか悲しくな
る。「なぜそこまでして怯えた状態に甘んじているのだろう?」とい
じわるな気持ちが頭をもたげる。「なぜそこから降りないの?」って。
ちょっと前に村上春樹の短編を読んだ。「七番目の男」。
幼少の頃に、目の前で亡くした友人の姿に怯えて生きる男の話。
彼はその友人にずっと責められた人生を送った。「助けようと思え
ば助けられた」という思いが、友人の姿をまとって彼を責め続けた。
よくある自責の念系なトラウマ物語である。
でも、村上春樹がその男に語らせる最後の言葉は心に残った。
「私は考えるのですが、この私たちの人生で真実怖いのは、恐怖
そのものではありません」、男は少しあとでそう言った。「恐怖はた
しかにそこにあります。・・・・・・それは様々なかたちをとって現れ、
ときとして私たちの存在を圧倒します。しかしなによりも怖いのは、
その恐怖に背中を向け、目を閉じてしまうことです。そうすることに
よって、私たちは自分の中にあるいちばん重要なものを、何かに
譲り渡してしまうことになります。私の場合には-それは波でした」
(村上春樹著『レキシントンの幽霊』所収「七番目の男」p.195)
恐怖心は必要である。でも悲しいのは、その恐怖に怯えるあまり
に、小手先ばかりのことを考えてしまう後ろ向きな姿勢だ。いや、
小手先どころではない。正対するのをなるべく回避しようとする、
その懐の狭隘さ。それが僕を沈んだ気持ちにさせる。
「そこまで怖いのなら辞めたらどうですか?」と、奥歯のあたりまで
出そうになる言葉を押しとどめる。でも、それは言えない。苦しくて
も辞められない事情は人それぞれあるのだから。そして僕にも。
でも「辞める」という言葉は常に持っておきたい。自分という人間の
自己満足な幸せのために(この僕が幸せでなければ、この人生は
いったい何なんだ)。そして、「辞めない」ことで被害を被る相手のた
めにも・・・・。そういう態度こそが一番の逃げであり、極めて後ろ向
きなのだよ、と言われそうである。
でも僕は、目の前にある大事なものを失いたくない。
恐怖に苛まれてばかりで、自分に与えられた幸せに気づかないな
んて嫌だ。怖いけどしっかりと向き合いたい。向き合って、悩んで
苦しんで、あえいで、じたばたして、堂々巡りをしても、そこにあるも
のは僕のために用意されたものだ。
だから必ず救いはあるし、幸せもある。はず。
そこに救いも幸せも見いだせなくなったとき、背を向けたくなったとき、
それはやはり潮時である。潮時にそれでもしがみつくなんてことは、
やはり僕にはできそうもない。
※抽象論でごめんなさい
担任という仕事に。そして生徒指導という公務に。
溺れつつある。悲しいかなほとんどが事務作業。「急ぎ」と書かれた
資料に追い回され目眩を感じたので、すべてを一度休止し、机の整
理から始める。主にファイリング。机がきれいになっていく過程で、
頭もすっきりしてくる。仕事の優先順位が見えてくる。
整理整頓。あなどれない。
忙しいと、やはりたくさんの人との接触がある。確認しないといけな
いことばかりだから。その中で、偶然にも怯えた人に何人か出逢う。
誰に。
権力に。上司に。保護者に。そして子どもに。
怯えることは大事であると思う。恐怖心は仕事を細やかなものにす
る。恐れのない者は、勢いで賄えなくなると廃る。そのことは、もう
経験上痛感している、つもり。だってもうすぐ35なのですから(とは
言いつつも、「お前の仕事は力業だな」と叱られることは多々ある。
まだ35の青二才とも言える)。
だけど、あまりに恐怖心を持っている人に出逢うと、何だか悲しくな
る。「なぜそこまでして怯えた状態に甘んじているのだろう?」とい
じわるな気持ちが頭をもたげる。「なぜそこから降りないの?」って。
ちょっと前に村上春樹の短編を読んだ。「七番目の男」。
幼少の頃に、目の前で亡くした友人の姿に怯えて生きる男の話。
彼はその友人にずっと責められた人生を送った。「助けようと思え
ば助けられた」という思いが、友人の姿をまとって彼を責め続けた。
よくある自責の念系なトラウマ物語である。
でも、村上春樹がその男に語らせる最後の言葉は心に残った。
「私は考えるのですが、この私たちの人生で真実怖いのは、恐怖
そのものではありません」、男は少しあとでそう言った。「恐怖はた
しかにそこにあります。・・・・・・それは様々なかたちをとって現れ、
ときとして私たちの存在を圧倒します。しかしなによりも怖いのは、
その恐怖に背中を向け、目を閉じてしまうことです。そうすることに
よって、私たちは自分の中にあるいちばん重要なものを、何かに
譲り渡してしまうことになります。私の場合には-それは波でした」
(村上春樹著『レキシントンの幽霊』所収「七番目の男」p.195)
恐怖心は必要である。でも悲しいのは、その恐怖に怯えるあまり
に、小手先ばかりのことを考えてしまう後ろ向きな姿勢だ。いや、
小手先どころではない。正対するのをなるべく回避しようとする、
その懐の狭隘さ。それが僕を沈んだ気持ちにさせる。
「そこまで怖いのなら辞めたらどうですか?」と、奥歯のあたりまで
出そうになる言葉を押しとどめる。でも、それは言えない。苦しくて
も辞められない事情は人それぞれあるのだから。そして僕にも。
でも「辞める」という言葉は常に持っておきたい。自分という人間の
自己満足な幸せのために(この僕が幸せでなければ、この人生は
いったい何なんだ)。そして、「辞めない」ことで被害を被る相手のた
めにも・・・・。そういう態度こそが一番の逃げであり、極めて後ろ向
きなのだよ、と言われそうである。
でも僕は、目の前にある大事なものを失いたくない。
恐怖に苛まれてばかりで、自分に与えられた幸せに気づかないな
んて嫌だ。怖いけどしっかりと向き合いたい。向き合って、悩んで
苦しんで、あえいで、じたばたして、堂々巡りをしても、そこにあるも
のは僕のために用意されたものだ。
だから必ず救いはあるし、幸せもある。はず。
そこに救いも幸せも見いだせなくなったとき、背を向けたくなったとき、
それはやはり潮時である。潮時にそれでもしがみつくなんてことは、
やはり僕にはできそうもない。
※抽象論でごめんなさい
Posted by sky1973629 at 00:14│Comments(4)
│日常
この記事へのコメント
私は忙しさに忙殺された事がないのでその件に関しては分かりませんが、恐怖心がある時、嫌な事があった時はなぜだか無性に眠くなる。眠りに逃げている感がある。でもそれでも眠る事は私の心の助けになっているので、それはそれで私にとってはOKなのかも。
Posted by 凛MM at 2008年05月29日 00:28
僕の新しい職場がらみではいわゆる公務員系の方が多いので、
彼らの責任回避が故の言動や行動が目に付きそうな予感が大です。
すでに何件かそのように感じる瞬間ありました。
でも、僕は少しおつむ悪そうに「ねえ、なんで?なんで?」
「できそうよね。うん。ほらできた〜」
なんて、いつか書いたジョンレノン話のように
実践しようと思ってるよ。
だって、結果、美味しいビールが飲みたいもの〜
優しく厳しく生きるのだ。
難しいけどね。。。
彼らの責任回避が故の言動や行動が目に付きそうな予感が大です。
すでに何件かそのように感じる瞬間ありました。
でも、僕は少しおつむ悪そうに「ねえ、なんで?なんで?」
「できそうよね。うん。ほらできた〜」
なんて、いつか書いたジョンレノン話のように
実践しようと思ってるよ。
だって、結果、美味しいビールが飲みたいもの〜
優しく厳しく生きるのだ。
難しいけどね。。。
Posted by みやじま at 2008年05月29日 01:59
at 2008年05月29日 01:59
 at 2008年05月29日 01:59
at 2008年05月29日 01:59よんな〜よんな〜で良いんだよ(^O^)焦らずゆっくり行こう(^O^)大丈夫誰かがきっと見ててくれるからね
Posted by ☆ぽろりん☆ at 2008年05月29日 09:44
凛MMさん、みやじまくん、☆ぽろりん☆さん>
いつも小言に付き合ってくれて、ありがと。センシティブでセンチメンタルでアグレッシブでラディカルな、そういういろいろな顔で生きていける人間になれたらいいな。
いつも小言に付き合ってくれて、ありがと。センシティブでセンチメンタルでアグレッシブでラディカルな、そういういろいろな顔で生きていける人間になれたらいいな。
Posted by コメスセイキ at 2008年05月29日 22:07