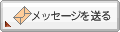2013年01月06日
冬休みのお仕事③
教師はありがたい仕事。
春休み夏休み冬休みと定期的にリセットでき、充電できる。
もちろん普段はなかなかとれない有給を使ってしっかり休
養し解放されることも大事。元気と志気を取り戻すことも、
教師にとっては大事なこと。その間に家族孝行も親孝行も
しなきゃいけない・・・し。
でももちろん、充電しレベルアップしなきゃいけないことは
論を待たない。これは使命職である教師の使命。加齢に
伴う見た目は残念ながら変えることはできないので(涙)、
中身を磨くリビジョンアップくらいはしよう。
と思い、まずはいつもせっせと本を読む。
冬休みは親の介護と正月の間に、斜め読みも含めて
以下の本らを読んだ。
北尾吉孝著『森信三に学ぶ』(致知出版社)
野口芳宏著『教師のための話す作法』(学陽書房)
吉田高志編『写真類読み取りの授業』(明治図書)
林竹二・灰谷健次郎著『教えることと学ぶこと』(倫書房)
梶尾叡一著『教師力再興』(明治図書)
水内喜久雄選『谷川俊太郎詩集・いまぼくに』(理論社)
井上ひさし著『子どもにつたえる日本国憲法』(講談社)
池田香代子訳『やさしいことばで日本国憲法』(マガジンハウス)
そして締めくくりはやっぱり同じ。毎年読む本。

向山先生の文章を通して、改めて子どもたちが好きになる。
早く授業がしたい!と思えてくる。使命を果たそうと帯をしめ
なおす。そして残りわずかな期間を精一杯走り抜けようと気
持ちが定まる。
定まったところで、冬休みの仕事の総仕上げ。三学期最初
の学級通信を一気通貫で書き上げる。こんな文章。
2013年。新しい年の始まり、皆さんは今年の抱負を持ちま
したか?「一年の計は元旦にあり」と言われます。これは、ど
んな一年になるかは、年を明けた時に抱く計画で決まるという
先人の教えです。少々大げさかもしれませんが、先人が言い
たかったことは分かります。人は心持ちでいかようにも変われ
るということです。人間は柔軟な生き物なのです。でもだから
こそ「今日からこうしよう!」「今年はこれを精一杯取り組もう
!」と強く思い願わない限り、人は変わりません。人は易きに
流れる生き物です。自分が成長できると信じ、一つずつ意識
的に努力することなしに、人は変われないのです。
あと51日で卒業です(早いね)。すぐに中学生です。親や先
生から言われたことをただやるだけじゃなく、自分の未来をし
っかりとイメージして、全力で取り組み一歩ずつ成長していく。
今年をその新たなスタートにして欲しいと思います。「初志貫徹
~魅せろ38期生~」という三学期の学年テーマには、その思
いが込められています。自分が目指したところに向かって力一
杯走りきり、成長した新しい自分と出会ってください。「やれば
できた!」と思ってください。その時、その姿が「魅せる」ことそ
のものだと思います。もちろん、それを支えるのが6年担任の
先生の仕事です。一つも手を抜かず先生も全力疾走します!
一緒に走りきりましょう。
春休み夏休み冬休みと定期的にリセットでき、充電できる。
もちろん普段はなかなかとれない有給を使ってしっかり休
養し解放されることも大事。元気と志気を取り戻すことも、
教師にとっては大事なこと。その間に家族孝行も親孝行も
しなきゃいけない・・・し。
でももちろん、充電しレベルアップしなきゃいけないことは
論を待たない。これは使命職である教師の使命。加齢に
伴う見た目は残念ながら変えることはできないので(涙)、
中身を磨くリビジョンアップくらいはしよう。
と思い、まずはいつもせっせと本を読む。
冬休みは親の介護と正月の間に、斜め読みも含めて
以下の本らを読んだ。
北尾吉孝著『森信三に学ぶ』(致知出版社)
野口芳宏著『教師のための話す作法』(学陽書房)
吉田高志編『写真類読み取りの授業』(明治図書)
林竹二・灰谷健次郎著『教えることと学ぶこと』(倫書房)
梶尾叡一著『教師力再興』(明治図書)
水内喜久雄選『谷川俊太郎詩集・いまぼくに』(理論社)
井上ひさし著『子どもにつたえる日本国憲法』(講談社)
池田香代子訳『やさしいことばで日本国憲法』(マガジンハウス)
そして締めくくりはやっぱり同じ。毎年読む本。
向山先生の文章を通して、改めて子どもたちが好きになる。
早く授業がしたい!と思えてくる。使命を果たそうと帯をしめ
なおす。そして残りわずかな期間を精一杯走り抜けようと気
持ちが定まる。
定まったところで、冬休みの仕事の総仕上げ。三学期最初
の学級通信を一気通貫で書き上げる。こんな文章。
2013年。新しい年の始まり、皆さんは今年の抱負を持ちま
したか?「一年の計は元旦にあり」と言われます。これは、ど
んな一年になるかは、年を明けた時に抱く計画で決まるという
先人の教えです。少々大げさかもしれませんが、先人が言い
たかったことは分かります。人は心持ちでいかようにも変われ
るということです。人間は柔軟な生き物なのです。でもだから
こそ「今日からこうしよう!」「今年はこれを精一杯取り組もう
!」と強く思い願わない限り、人は変わりません。人は易きに
流れる生き物です。自分が成長できると信じ、一つずつ意識
的に努力することなしに、人は変われないのです。
あと51日で卒業です(早いね)。すぐに中学生です。親や先
生から言われたことをただやるだけじゃなく、自分の未来をし
っかりとイメージして、全力で取り組み一歩ずつ成長していく。
今年をその新たなスタートにして欲しいと思います。「初志貫徹
~魅せろ38期生~」という三学期の学年テーマには、その思
いが込められています。自分が目指したところに向かって力一
杯走りきり、成長した新しい自分と出会ってください。「やれば
できた!」と思ってください。その時、その姿が「魅せる」ことそ
のものだと思います。もちろん、それを支えるのが6年担任の
先生の仕事です。一つも手を抜かず先生も全力疾走します!
一緒に走りきりましょう。
2013年01月06日
冬休みのお仕事②
さてさて、散らかった心も次第にまとまり始めたので、次の仕事
に取りかかる。
次はこれこれ。貸し出し文具。

僕は子どもたちが忘れ物をしたら、基本として「貸してあげる」。
鉛筆も赤鉛筆も、定規もネームペンも、辞書も赤白帽も・・・。
持ち出しになるけれど、可能なものは全部貸してあげようと思っ
ている。忘れ物は人間の常。助けてあげて、置いてけぼりにな
らないようにしてあげるのは、日中の親代わりである担任の仕
事として重視している。
もちろん!
忘れ物が続く子にはプレスする。「3回忘れたら親に協力しても
らいます」と告げ、本当に3回続けて忘れたら親に連絡を入れ、
学習用具の準備を手伝ってもらうようお願いする。
でも、たまに「あっ!忘れちゃった~」となった時は快く助ける。
①忘れたことをきちんと報告する、②謝る、③貸してくれと頼む、
④用がすんだらお礼を言って返却する。この4点セットをきちん
とこなせば何の見返りもなく、「どうぞ」と貸す。
でもでも、忘れ物をした子に厳しく指導する先生を見ると、「自分
は甘いかな~」と思うこともある。貸してくれることに頼りっぱなし
で忘れ物が一向によくならない子を指導する場合にも然り。
でもでもでも、やっぱり成長途中の子らなのである。6年生であっ
てもまだまだ幼い子たち。だから長い目でつきあいたいし、安心
して学習に取り組んでほしいし、忘れ物が続くような子とはコミュ
ニケーションも増やしたい。だから、僕の場合には「貸せる」という
方法を取ることにしている。
初日に何を話そうかなと考えながら、一本一本鉛筆をせっせと
削る。ずっと主が現れない拾い物から体育着や赤白帽も数着
いただき、洗濯して棚におさめる。準備完了。
こういうことをせっせとしているうちに、次第に担任面になって
きた。リハビリもあと一踏ん張り。
追記:おすすめの鉛筆と赤鉛筆。どうせ貸せるなら最高のもの
を使わ、良さを実感させたい。滑らずしっかり書けるよ。後ろの
ちょい削りは「先生のもの!」印であります。

に取りかかる。
次はこれこれ。貸し出し文具。
僕は子どもたちが忘れ物をしたら、基本として「貸してあげる」。
鉛筆も赤鉛筆も、定規もネームペンも、辞書も赤白帽も・・・。
持ち出しになるけれど、可能なものは全部貸してあげようと思っ
ている。忘れ物は人間の常。助けてあげて、置いてけぼりにな
らないようにしてあげるのは、日中の親代わりである担任の仕
事として重視している。
もちろん!
忘れ物が続く子にはプレスする。「3回忘れたら親に協力しても
らいます」と告げ、本当に3回続けて忘れたら親に連絡を入れ、
学習用具の準備を手伝ってもらうようお願いする。
でも、たまに「あっ!忘れちゃった~」となった時は快く助ける。
①忘れたことをきちんと報告する、②謝る、③貸してくれと頼む、
④用がすんだらお礼を言って返却する。この4点セットをきちん
とこなせば何の見返りもなく、「どうぞ」と貸す。
でもでも、忘れ物をした子に厳しく指導する先生を見ると、「自分
は甘いかな~」と思うこともある。貸してくれることに頼りっぱなし
で忘れ物が一向によくならない子を指導する場合にも然り。
でもでもでも、やっぱり成長途中の子らなのである。6年生であっ
てもまだまだ幼い子たち。だから長い目でつきあいたいし、安心
して学習に取り組んでほしいし、忘れ物が続くような子とはコミュ
ニケーションも増やしたい。だから、僕の場合には「貸せる」という
方法を取ることにしている。
初日に何を話そうかなと考えながら、一本一本鉛筆をせっせと
削る。ずっと主が現れない拾い物から体育着や赤白帽も数着
いただき、洗濯して棚におさめる。準備完了。
こういうことをせっせとしているうちに、次第に担任面になって
きた。リハビリもあと一踏ん張り。
追記:おすすめの鉛筆と赤鉛筆。どうせ貸せるなら最高のもの
を使わ、良さを実感させたい。滑らずしっかり書けるよ。後ろの
ちょい削りは「先生のもの!」印であります。
2013年01月05日
冬休みのお仕事①
明けました2013年。
今年は息子のたっての願いを聞き入れて、彼ら初の神宮参り。
息子らは念願のおみくじ。二人とも中吉・・・。まあまあですね~
と笑いながら僕はひかず。小心者の人間にとっておみくじは身
体に悪い。100円投げて、「ベストを尽くします。どうぞ元気で
働かせてください」と神頼みで十二分とする。
あまりたくさん持ってないけれど、誠心を尽くそう。
尽きない欲望はなるべく抑えて、清福を味わおう。
自己主張をする前に、まず人の話をしかと聴こう。
そう決めた一年。お天道様、どうぞよろしくお願いします。
さてさて、年末は親の介護で費やしてしまい、ほとんど学校に
行けなかった。学校から離れた期間が少々長かったせいかな、
なかなかエンジンがかからない。「おいおいがんばろうーぜ」と
担任リハビリを始める。
一番最初にやるのは、やはり掃除。掃除。掃除。
学期末にみんなで大掃除をしてある程度はキレイになってる
のだけれど、仕上げは担任の仕事。

僕ら教員が真っ先にやらなきゃいけない仕事は、やっぱり環
境整備だと思っている。「掃除は子どもにさせなきゃ意味がな
い」と厚顔に言って徹底的に掃除をさせる方々がいるけれど、
僭越ながら、それは無知ではなかろうかと僕は思っている。
子どもは決して「掃除や」ではない。
僕ら教師が子どもたちにさせているのは「清掃学習」なのであ
り、「清掃」そのものではない。「清掃」の意義、つまり衛生の大
事さや気持ち良さ、効率的な術、協力などを教えるのが「清掃
学習」。だからそれらがある程度達成できれば、掃除に不十分
なところがあっても僕は差し支えない。残りは教室の管理者た
る担任の仕事に他ならない。
だから、せっせとやる。机を寄せながら、ロッカーをふきなが
ら、次第に子どもたちの顔が具体的に浮かんでくる。拾いも
のから学級の様子も見えてくる。「これ指導しなきゃいけない
な」とか「こういうのしっかり見ていかなきゃいけないな」と自
分と学級の課題がはっきりしてくる。これをせっせとメモする。
特に力を入れるのが生理的な感情が湧くところ。


学校はストレスのかかる場所。どんなに楽しいことをしたっ
てそれに違いはない。というよりも、一定のストレスをかけ
て成長を促すのが役目、とも言える。だから、なるべく生活
スペースで嫌な気分にさせたくない。とりわけ生理的な感
情が惹起されるところは熱心に。
カビキラーをまきまき、たわしでごしごし、ぞうきんでキュッ
キュッと拭いて完成。昨日と今日とで2日かければかなり
きれいになった。ふぃー。
頭巾に作業着ズボン。格好はただの大掃除をするおっさん
ですけど、思考は次第に教師モードに。
散らかっていた気分もまとまり始めてきた。
さあて、また演じてみようかと思う。
今年は息子のたっての願いを聞き入れて、彼ら初の神宮参り。
息子らは念願のおみくじ。二人とも中吉・・・。まあまあですね~
と笑いながら僕はひかず。小心者の人間にとっておみくじは身
体に悪い。100円投げて、「ベストを尽くします。どうぞ元気で
働かせてください」と神頼みで十二分とする。
あまりたくさん持ってないけれど、誠心を尽くそう。
尽きない欲望はなるべく抑えて、清福を味わおう。
自己主張をする前に、まず人の話をしかと聴こう。
そう決めた一年。お天道様、どうぞよろしくお願いします。
さてさて、年末は親の介護で費やしてしまい、ほとんど学校に
行けなかった。学校から離れた期間が少々長かったせいかな、
なかなかエンジンがかからない。「おいおいがんばろうーぜ」と
担任リハビリを始める。
一番最初にやるのは、やはり掃除。掃除。掃除。
学期末にみんなで大掃除をしてある程度はキレイになってる
のだけれど、仕上げは担任の仕事。
僕ら教員が真っ先にやらなきゃいけない仕事は、やっぱり環
境整備だと思っている。「掃除は子どもにさせなきゃ意味がな
い」と厚顔に言って徹底的に掃除をさせる方々がいるけれど、
僭越ながら、それは無知ではなかろうかと僕は思っている。
子どもは決して「掃除や」ではない。
僕ら教師が子どもたちにさせているのは「清掃学習」なのであ
り、「清掃」そのものではない。「清掃」の意義、つまり衛生の大
事さや気持ち良さ、効率的な術、協力などを教えるのが「清掃
学習」。だからそれらがある程度達成できれば、掃除に不十分
なところがあっても僕は差し支えない。残りは教室の管理者た
る担任の仕事に他ならない。
だから、せっせとやる。机を寄せながら、ロッカーをふきなが
ら、次第に子どもたちの顔が具体的に浮かんでくる。拾いも
のから学級の様子も見えてくる。「これ指導しなきゃいけない
な」とか「こういうのしっかり見ていかなきゃいけないな」と自
分と学級の課題がはっきりしてくる。これをせっせとメモする。
特に力を入れるのが生理的な感情が湧くところ。
学校はストレスのかかる場所。どんなに楽しいことをしたっ
てそれに違いはない。というよりも、一定のストレスをかけ
て成長を促すのが役目、とも言える。だから、なるべく生活
スペースで嫌な気分にさせたくない。とりわけ生理的な感
情が惹起されるところは熱心に。
カビキラーをまきまき、たわしでごしごし、ぞうきんでキュッ
キュッと拭いて完成。昨日と今日とで2日かければかなり
きれいになった。ふぃー。
頭巾に作業着ズボン。格好はただの大掃除をするおっさん
ですけど、思考は次第に教師モードに。
散らかっていた気分もまとまり始めてきた。
さあて、また演じてみようかと思う。
2012年12月26日
カタコト
来年の年賀状を作ってます。
今年の言葉は「誠心清福」。
偽りのない心で、穏やかで慎ましい幸せを感じたいと思うこの頃です。
でも
偽りのない心はときに敵を作ります。
世知辛ければ辛いほどに、敵は増えていきます。
だから
偽りのない心とは戦う心なのです。
コツコツとやってみようと思います。
決してくじけずに、戦い続けてみようと思います。
はた迷惑なエゴを少しと譲れない責任感
そして地味で地道な継続性の中で
戦ってみようと思います。
そこに、身の丈の幸せがあればいいな
と
そこに、安らぎさえあればいいな
と切に思います。
今年の言葉は「誠心清福」。
偽りのない心で、穏やかで慎ましい幸せを感じたいと思うこの頃です。
でも
偽りのない心はときに敵を作ります。
世知辛ければ辛いほどに、敵は増えていきます。
だから
偽りのない心とは戦う心なのです。
コツコツとやってみようと思います。
決してくじけずに、戦い続けてみようと思います。
はた迷惑なエゴを少しと譲れない責任感
そして地味で地道な継続性の中で
戦ってみようと思います。
そこに、身の丈の幸せがあればいいな
と
そこに、安らぎさえあればいいな
と切に思います。
2012年12月08日
机に付着いています
評価の時期なのです(涙)。机にべったりとくっつき資料とにらめっこしつつ、
ひたすら書き込む書き込む・・・。腕が痛くなり集中が途切れる。そんな辛い
隙間に近況でも書いてみます。
明後日は琉球大学の子たちに呼ばれてプチ講師。こんなやつを使ってくれ
るなら、僕は何処にでも行きます。人の役に立つことこそ「やりがい」ってね、
子どもたちとこの前勉強したばかり。ってそんなもんじゃないのよ、人に求め
られるってのはね、僕にとってはそれはもう生きてる甲斐そのもの。オレの
これまでって捨てたもんじゃないと・・・自尊感情がメラメラムキムキと・・・。
ホントありがたい限りです。

テーマは何にしようかなと思案しつつ、ふと降りてきたものを即メモメモ。
僕たちがこの6年間で学んできたものが授業でどう活かされているのか、
僕にもまだ整理がつかない。それを志多き学生さんたちと考えてみよう
かな。
ひたすら書き込む書き込む・・・。腕が痛くなり集中が途切れる。そんな辛い
隙間に近況でも書いてみます。
明後日は琉球大学の子たちに呼ばれてプチ講師。こんなやつを使ってくれ
るなら、僕は何処にでも行きます。人の役に立つことこそ「やりがい」ってね、
子どもたちとこの前勉強したばかり。ってそんなもんじゃないのよ、人に求め
られるってのはね、僕にとってはそれはもう生きてる甲斐そのもの。オレの
これまでって捨てたもんじゃないと・・・自尊感情がメラメラムキムキと・・・。
ホントありがたい限りです。
テーマは何にしようかなと思案しつつ、ふと降りてきたものを即メモメモ。
僕たちがこの6年間で学んできたものが授業でどう活かされているのか、
僕にもまだ整理がつかない。それを志多き学生さんたちと考えてみよう
かな。
2012年09月29日
堂々巡りではいけないのよね
いろいろあった夏だった。僕は元気なのだけど、その周辺でドタンバタンといろいろと。ようやく落ち着きを見せてきたけれど、気ぜわしいのは変わらない。
おかげさまで様々な覚悟もできた。少しまたおとなになったかな。いやおじさんにね。
何だか無性に本を読みたくなって、棚から本をとったら、そこに十数年も前にやったんだろうと思われる折り目が。
「そういう考え方は本当にくだらないと僕は思う」と僕は言った。「後悔するくらいなら君ははじめからきちんと公平に彼に接しておくべきだったんだ。少なくとも公平になろうという努力くらいはするべきだったんだ。(略)「ねえ、いいかい、ある種の物事というのは口に出してはいけないんだ。口に出したらそれはそこで終わってしまうんだ。身につかない。君はディック・ノースに対して後悔する。そして後悔していると言う。本当にしているんだろうと思う。でももし僕がディック・ノースだったら、僕は君にそんな風に簡単に後悔なんかしてほしくない」(村上春樹『ダンス・ダンス・ダンス』)
口ばっか先に出る今日この頃。おじさんになってしまった分、余計にたちが悪くなってきたようにさえ思う。同じところをぐるぐると周り、愚痴と後悔をまきちらし、疲れ果て、わずかな出口を見つけてはまた同じことを繰り返す。まったく身についてない。十数年前の学びを忘れていた僕に、僕は改めてその空しさを教えてくれた。
これは子どもたちからアップするように言われ続けてた写真。うちの学級のアイドルとそれを脅かす猛獣。なんのこっちゃ。

おかげさまで様々な覚悟もできた。少しまたおとなになったかな。いやおじさんにね。
何だか無性に本を読みたくなって、棚から本をとったら、そこに十数年も前にやったんだろうと思われる折り目が。
「そういう考え方は本当にくだらないと僕は思う」と僕は言った。「後悔するくらいなら君ははじめからきちんと公平に彼に接しておくべきだったんだ。少なくとも公平になろうという努力くらいはするべきだったんだ。(略)「ねえ、いいかい、ある種の物事というのは口に出してはいけないんだ。口に出したらそれはそこで終わってしまうんだ。身につかない。君はディック・ノースに対して後悔する。そして後悔していると言う。本当にしているんだろうと思う。でももし僕がディック・ノースだったら、僕は君にそんな風に簡単に後悔なんかしてほしくない」(村上春樹『ダンス・ダンス・ダンス』)
口ばっか先に出る今日この頃。おじさんになってしまった分、余計にたちが悪くなってきたようにさえ思う。同じところをぐるぐると周り、愚痴と後悔をまきちらし、疲れ果て、わずかな出口を見つけてはまた同じことを繰り返す。まったく身についてない。十数年前の学びを忘れていた僕に、僕は改めてその空しさを教えてくれた。
これは子どもたちからアップするように言われ続けてた写真。うちの学級のアイドルとそれを脅かす猛獣。なんのこっちゃ。
2012年06月09日
生徒指導主任なので
主任になって7年になる。7年。
この長さは普通じゃない。これは明らかに因果応報よね。天の采配。
なので、これまでいろいろと考えてきたこと、実践してきたこと、うまくいったこと、失敗したことなどなど、みんなに知らせていこうかなと思ってたところ、軌を一にして、ボスからも命じられた。
第一弾はこんなことを話しました。
____________________________________
(1)明確な指標(行動指標)を持たせる。
何が良くて何が悪いのかというのを分かりやすく教える。
(2)作業確認をせっせとする。
一度教えたことを簡単に手放さず、日々せっせと「どうだった?」と確認する。
(3)レベルを上げる。~「褒める」ことを大事にする
何よりも子どもを伸ばすのは「具体的に褒める」ということ。小さなことも見逃さず、その場で具体的に褒めること。それが他の子にも伝播するのが他でもない学級という場。
(4)叱るときは叱る。
立たせる。理由を言わせる。その何が悪いのか考えさせる。「はい」と言わせて肯定的に終わる。頭ごなしに大声で一方的に叱ることはしない。
(5)長い目で育てる。
一度の指導ですべてをやり遂げようと思うとき過剰になる。ゆっくり育てていけばいい。担任はそんな一進一退を繰り返しゆっくり育っていく子らを周囲から守ってやるのが仕事。
___________________________________
拙いもんですけど、これがきっかけになってみんなからレスポンスがあればいいさ。そのレスポンスへのレスポンスが積み重なって、全体が向上できればいいさあね。
この長さは普通じゃない。これは明らかに因果応報よね。天の采配。
なので、これまでいろいろと考えてきたこと、実践してきたこと、うまくいったこと、失敗したことなどなど、みんなに知らせていこうかなと思ってたところ、軌を一にして、ボスからも命じられた。
第一弾はこんなことを話しました。
____________________________________
(1)明確な指標(行動指標)を持たせる。
何が良くて何が悪いのかというのを分かりやすく教える。
(2)作業確認をせっせとする。
一度教えたことを簡単に手放さず、日々せっせと「どうだった?」と確認する。
(3)レベルを上げる。~「褒める」ことを大事にする
何よりも子どもを伸ばすのは「具体的に褒める」ということ。小さなことも見逃さず、その場で具体的に褒めること。それが他の子にも伝播するのが他でもない学級という場。
(4)叱るときは叱る。
立たせる。理由を言わせる。その何が悪いのか考えさせる。「はい」と言わせて肯定的に終わる。頭ごなしに大声で一方的に叱ることはしない。
(5)長い目で育てる。
一度の指導ですべてをやり遂げようと思うとき過剰になる。ゆっくり育てていけばいい。担任はそんな一進一退を繰り返しゆっくり育っていく子らを周囲から守ってやるのが仕事。
___________________________________
拙いもんですけど、これがきっかけになってみんなからレスポンスがあればいいさ。そのレスポンスへのレスポンスが積み重なって、全体が向上できればいいさあね。
2012年05月28日
未来にではなく
ヒトに自分がいなくなった日
ヒトはたがいにとても似ていた
ヒトに自分がいなくなった日
ヒトは未来を信じつづけた
谷川俊太郎「空に小鳥がいなくなった日」
今日はオフ。自分を未来に託さない、そんな自分のための自分の一日を過ごそうと思う。
って、もうすでに午後。グスン。数時間後には子らのお迎え。
2012年05月27日
佇まい
この写真になぜかにっこりする。疲れた夜も明るい気分になる。

かの灰谷健次郎さん。もう亡くなってずいぶんとなるけど、古本屋で見つけてきた本の表紙。彼が街を出て島で暮らしはじめた頃のもの。そんなおっちゃんが好きなの!?って話ではなく、この人の佇まいが僕の何かを異様に惹き付ける。
神戸の殺人事件のとき、その報道ぶりに灰谷さんはめちゃくちゃ怒っていた。そのずいぶんと強い口調に閉口したこと、その口ぶりにある種の権力性を感じたことを今でもなんとなく覚えている。
でも、本屋で出会ったこの写真に、僕はドキドキッとしてしまった。「こんな佇まいのおっちゃんだったんだ・・・」と、彼のことをよく知らないままに敬遠していた自分を恥じた。いやいや、佇まいだけで灰谷さんの何が分かるというわけではない。まったくない。でもね、なんだか直感が疼く。いわば無防備に他者に開いたこの佇まいは、まるでまんま子どものようで、持ちつ持たれつの人生の機微を大ぴらに差し出しているように感じてしかたがない。
僕はこういう佇まいで、人と接する人間にこそなりたい。
かの灰谷健次郎さん。もう亡くなってずいぶんとなるけど、古本屋で見つけてきた本の表紙。彼が街を出て島で暮らしはじめた頃のもの。そんなおっちゃんが好きなの!?って話ではなく、この人の佇まいが僕の何かを異様に惹き付ける。
神戸の殺人事件のとき、その報道ぶりに灰谷さんはめちゃくちゃ怒っていた。そのずいぶんと強い口調に閉口したこと、その口ぶりにある種の権力性を感じたことを今でもなんとなく覚えている。
でも、本屋で出会ったこの写真に、僕はドキドキッとしてしまった。「こんな佇まいのおっちゃんだったんだ・・・」と、彼のことをよく知らないままに敬遠していた自分を恥じた。いやいや、佇まいだけで灰谷さんの何が分かるというわけではない。まったくない。でもね、なんだか直感が疼く。いわば無防備に他者に開いたこの佇まいは、まるでまんま子どものようで、持ちつ持たれつの人生の機微を大ぴらに差し出しているように感じてしかたがない。
僕はこういう佇まいで、人と接する人間にこそなりたい。
2012年05月15日
さあてね
扉を開けて 中へお入り・・・
知らない世界へ出かけよう
(折原みと)
敬愛する加藤せんせいからご本をいただいた。自費出版もの。苦心もの(経済的にね)。その中の冒頭に引用された詩。
ドキドキするし、何よりもワクワクする。そんな鋭い言葉をさらっと言える人になら、こんな平べったい日常なのだから、ついて行きたくなる。そんな何気ない引用に心奪われる僕は黄色信号。
ぼーっとするそんな僕に、壁に貼ったフーコーが呼びかける。目の前に貼ってあるから否が応でも。
夢見るためには眼を閉じていてはならない。〈読むこと〉である。
さあて、相変わらず現実的にがんばろう。。。かね。
知らない世界へ出かけよう
(折原みと)
敬愛する加藤せんせいからご本をいただいた。自費出版もの。苦心もの(経済的にね)。その中の冒頭に引用された詩。
ドキドキするし、何よりもワクワクする。そんな鋭い言葉をさらっと言える人になら、こんな平べったい日常なのだから、ついて行きたくなる。そんな何気ない引用に心奪われる僕は黄色信号。
ぼーっとするそんな僕に、壁に貼ったフーコーが呼びかける。目の前に貼ってあるから否が応でも。
夢見るためには眼を閉じていてはならない。〈読むこと〉である。
さあて、相変わらず現実的にがんばろう。。。かね。